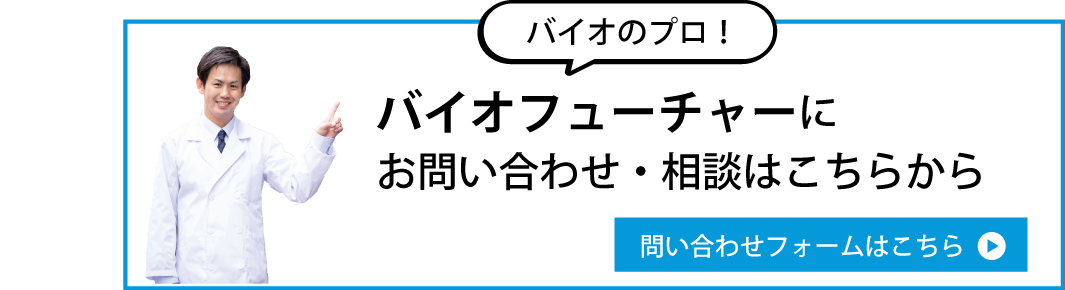アオコがメダカ飼育に与える悪影響と対策方法を解説します!


アオコとは?メダカ飼育に与える影響
メダカを飼育していると、水槽の水が緑色に濁ることがあります。その原因は、もしかしたら「アオコ」かもしれません。
アオコとは、藍藻類と呼ばれる微細な植物プランクトンが大量発生し、水面が緑色に濁る現象のことを言います。一見、アオコと同じ緑色をしている「グリーンウォーター」と混同されがちですが、アオコは水質悪化のサインであり、放置するとメダカに悪影響を及ぼす可能性があります。
水槽が濃い緑色に変化したときや悪臭がするときは、まずアオコの発生を疑い、早急に対処する必要があります。
このコラムでは、アオコの発生原因やメダカへの影響、そしてアオコが発生した場合の対策方法について詳しく解説しますので、参考になさってください。
アオコの正体とは?グリーンウォーターとの違い
アオコは主に「シアノバクテリア(藍藻)」と呼ばれる微生物で、植物プランクトンの一種です。アオコの大量発生は、水質のバランスを大きく崩す原因となり、水中の酸素濃度が低下したり、特有の悪臭が発生したりすることがあります。
一方、メダカの飼育に利用される「グリーンウォーター」ですが、アオコとの違いは何でしょうか。それは、発生する植物プランクトンにあります。

グリーンウォーターは、主にクロレラなど緑藻と呼ばれる植物性プランクトンが繁殖したもので、メダカの稚魚の成長を助ける栄養源にもなるとされています。また、アオコには悪臭がありますが、グリーンウォーターはそこまでにおいません。透明度は低くなるものの、水質が安定していればメダカへの悪影響は少なく、あえて飼育環境に利用されることもあります。
このように、アオコとグリーンウォーターは見た目が似ていても、発生する植物クランプトンや性質に大きな違いがあるのです。
アオコ発生によるメダカへの影響
アオコが発生した場合、メダカにどのような影響を与えるのでしょうか。
まず、アオコが水中で大量に繁殖すると、溶存酸素が消費されるため、水中の酸素濃度が低下しやすくなります。特に、夜間は光合成が行われないため、メダカが酸欠状態に陥るリスクが高くなります。
また、アオコ自体にも毒性を含んでおり、これが水中に放出されると、メダカの健康が損なわれることがあります。メダカが長時間そのような環境にさらされると、病気の発症率が高まり、最悪の場合は死滅につながることもあるでしょう。
見た目ではグリーンウォーターと区別がつきにくいこともありますが、水のにおいや透明度の変化、メダカの様子に注意を払い、アオコの兆候を見逃さないことが大切です。
メダカ飼育におけるその他の影響
アオコが発生すると水面が濃い緑色に変わり、水槽全体の見た目が悪くなります。水が透明でない状態が続くと、メダカの観察が難しくなるだけでなく、観賞の魅力が失われてしまいます。
また、アオコの繁殖によって特有の臭いが発生しやすくなり、屋内やベランダでの飼育において不快感の原因になることもあります。この悪臭は、アオコの死骸が分解されるときに発生するガスや有機物によるものです。
さらに、アオコの細かい粒子がフィルターやエアレーション装置に詰まることで、ろ過能力が低下したり、エアポンプの機能が落ちる可能性もあります。これにより、水質がさらに悪化し、メダカにとって過酷な環境となることもあります。
このような点からも、アオコの発生は見た目や水質面だけでなく、飼育全体にさまざまな影響を及ぼすため、日々の管理が重要になります。
メダカ飼育環境でアオコが発生する原因とは
メダカの飼育環境において、なぜアオコが発生するのでしょうか。

アオコの発生には、主に2つの大きな原因が関係しています。
①富栄養化(水中に過剰な栄養素が供給される)
②強い日光と高い水温
これらの要因が重なると、アオコの発生が加速し、メダカの飼育環境に悪影響を与えることがあります。水槽の水が緑色に濁ってしまった経験があり、その原因に思い当たる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここからは、アオコの発生原因について詳しく見ていきましょう。
メダカ飼育環境でアオコが発生する原因①富栄養化
「富栄養化」とは、水中にリンや窒素といった栄養塩が過剰に存在する状態を指し、これがアオコの大量発生を招く大きな要因となります。
メダカの飼育では、餌の食べ残しやフンが分解される過程で、栄養塩が水中に蓄積されやすくなります。これにより、アオコが繁殖しやすい環境が整ってしまうのです。特に、餌を過剰に与えてしまうと、食べきらなかった分が富栄養化を助長させ、アオコの発生リスクを高めます。
したがって、日々の管理においては、適切な餌の量を心がけることが非常に大切です。水中に余分な栄養素を溜めないようにすることが、アオコ発生の抑制につながります。
メダカ飼育環境でアオコが発生する原因②過剰な日光と水温の上昇による影響
アオコの発生は、日光と水温も大きく関係しています。
特に、春から夏にかけての暖かい時期、日光が直接水面に当たる環境では、アオコの光合成が活発になり、増殖スピードが一気に加速します。また、高い水温は微生物の代謝を促し、アオコが増えやすい状態を作り出します。
アオコの発生を防ぐには、水温と日照条件をコントロールすると効果的です。遮光ネットやすだれを活用して直射日光を防いだり、水槽を日陰に移動したりすれば、アオコの過剰な繁殖を防ぐことができます。
メダカにとって快適な環境を維持するためにも、日光と水温の管理に十分注意しましょう。
メダカの飼育でアオコが発生した場合の除去方法と対策
メダカの飼育でアオコが発生してしまった場合、メダカへの悪影響を防ぐためにも早めの対処が必要です。

アオコの発生を抑えるための方法として、大きく3つの対策があります。
- ・網やフィルターを使ってアオコを物理的に除去する
- ・専用の化学薬品を使用してアオコを抑える
- ・微生物の力を活用して水質を整えるバイオ製剤を使用する
これらの方法は、水槽の状況や目的にあわせて使い分けることが大切です。それぞれの特徴について、詳しくご説明しましょう。
アオコを物理的に除去
アオコが発生してしまった場合、まず試しやすいのが物理的な除去方法です。
具体的には、水面に浮いたアオコを網ですくったり、フィルターを使って水中の藻類を吸着・ろ過したりといった手段が挙げられます。また、水替えを行うことで一時的に水質を改善し、アオコの量を減らすことも可能です。
これらの方法は即効性があり、目に見える変化が期待できますが、その分手間がかかるうえに、一時しのぎに留まってしまうこともあります。根本的な原因、例えば、富栄養化や日光の当たりすぎといった環境要因を改善しないままでは、再びメダカの飼育環境にアオコが発生する可能性があります。
物理的な除去はあくまで応急処置ととらえ、メダカにとって快適な環境を維持するために、あわせて原因への対処を意識することが大切です。
化学薬品の使用
アオコの除去には、化学薬品を使用する方法もあります。市販されているアオコ対策用の薬剤には、藍藻類の活動を抑えたり、死滅させたりする成分が含まれているため、短期間で目に見える効果が得られることがあります。
ただし、薬剤の種類によっては、メダカにとっても有害となることがあり、使用には注意が必要です。安全性が確認された製品を選び、使用量や使用方法を必ず守ることが重要です。
また、薬品に頼りすぎず、水質や飼育環境そのものを見直すことも、あわせて検討すると良いでしょう。
バイオ製剤の使用
アオコの発生を抑える方法として、バイオ製剤の使用も効果的です。
バイオ製剤は、微生物の働きを利用して、水中のリンや窒素といった栄養分を分解・吸収し、アオコの繁殖を抑えます。富栄養化の原因となる物質を減らすことで、アオコが発生しにくい環境づくりにつながります。
また、化学薬品と異なり、バイオ製剤は一般的にメダカや他の水生生物に対する影響が少なく、安心して使用できる点も魅力です。継続的に使うことで、水質の安定化や透明度の向上にもつながる可能性があります。
バイオ製剤ごとに成分や使用条件が異なりますので、メダカ飼育に使用する前には説明書を十分確認しましょう。
おすすめのアオコ対策用バイオ製剤をご紹介
バイオフューチャーでは、メダカをはじめとした水生生物に優しい、アオコ対策用のバイオ製剤を取り揃えております。

バイオフューチャーが取り扱っているバイオ製剤は以下の4つです。
- 1. 液体バイオ製剤FM
- 2. 液体バイオ製剤ST
- 3. 液体バイオ製剤マイクロブリフト
- 4. 観賞池浄化用液体バイオ製剤
これらのバイオ製剤は、それぞれ異なるアプローチでアオコの発生を防ぎ、健全な水環境を作り出します。 バイオフューチャーの製剤は、自然由来の微生物の力で水質を改善し、メダカなどの水生生物にとって安全で快適な環境を整えます。これらを組み合わせて使用することで、アオコの繁殖を抑え、清潔で美しい水環境を作り出すことができます。
次に、各製剤について詳しくご紹介します。
1. 液体バイオ製剤FM
「液体バイオ製剤FM」は、好気性の微生物を主体とした液体製品で、アオコの発生要因の一つであるリンの除去や、底にたまった汚泥の分解を得意とします。この製剤により水中の栄養塩の蓄積を抑え、アオコが繁殖しにくい環境づくりをサポートします。
メダカの飼育環境においても、この製剤を使用することで、水質が改善され、より健康的な環境が維持されます。
また、COD(化学的酸素要求量)、BOD(生物学的酸素要求量)、SS(浮遊物質)といった水質指標の改善や、悪臭の低減といった効果も期待できます。メダカにとっても快適な水質を保つために役立つでしょう。
さらに「液体バイオ製剤ST」や「液体バイオ製剤マイクロブリフト」など、他の製品と併用することで、より高い相乗効果が見込める点も特長です。継続的な使用によって、水質の安定化と透明度の向上が促されます。
2. 液体バイオ製剤ST
「液体バイオ製剤ST」は、好気性の微生物を使用した液体製剤で、底にたまった汚泥や水中の有機物の分解に優れています。メダカを飼育している水槽などに使用することで、汚れた底床や水質を改善し、メダカが健康に暮らせる環境を維持できます。
アオコの繁殖を支える栄養分の多くは、こうした有機物の分解によって減らすことができるため、アオコ発生の予防や改善に役立ちます。
また、液体バイオ製剤FMと同様に、COD(化学的酸素要求量)やBOD(生物学的酸素要求量)、SS(浮遊物質)の低減、悪臭の抑制といった水質改善効果も期待できます。
「液体バイオ製剤FM」や「液体バイオ製剤マイクロブリフト」との併用により、それぞれの特性を活かしながら相乗的な効果が見込めるのも特長です。
3. 液体バイオ製剤マイクロブリフト
「液体バイオ製剤マイクロブリフト」は、好気性と嫌気性の微生物を配合しており、溶存酸素が不足しやすい環境でも優れた働きを発揮します。
アオコの栄養源となる汚泥の分解や、悪臭、BOD(生物学的酸素要求量)の低減にも効果があります。特に、アオコが大量発生した場合、酸素不足が問題となりやすいですが、マイクロブリフトはこの状態でも活躍します。汚泥を分解することで、水質を改善し、清潔で健康的な水環境を作り出します。
さらに、この製剤についても、前述の「液体バイオ製剤FM」や「液体バイオ製剤ST」との組み合わせで、より強力な効果を期待でき、アオコ除去の効率がアップします。
これにより、アオコの繁殖を抑えるとともに、全体的な水質の改善にもつながり、メダカの健康を守るための効果的な対策となります。
4. 観賞池浄化用液体バイオ製剤
「観賞池浄化用液体バイオ製剤」は、前述した「液体バイオ製剤FM」「液体バイオ製剤ST」「液体バイオ製剤マイクロブリフト」の3つの製剤を配合しています。この製品は特に、個人宅の池やビオトープ、小規模な景観池の水質改善に適しています。
「観賞池浄化用液体バイオ製剤」には、光合成細菌をはじめとする複数の微生物が含まれており、アオコの除去や底汚泥の分解、悪臭の低減に優れた効果を発揮します。これにより、水質が改善され、清潔で美しい水環境が保たれます。さらに、メダカなどの水生生物に対して無害であり、安全に使用できる点が特徴です。
「観賞池浄化用液体バイオ製剤」は、簡単な使い方で実感できる効果が得られるため、水質浄化を目指す方には非常におすすめです。
メダカ飼育でアオコが発生したら、バイオフューチャーにお任せください!
メダカ飼育においてアオコが発生してしまった場合は、バイオフューチャーにお任せください。

バイオフューチャーは、微生物の力を活用した「バイオレメディエーション」技術に特化した会社です。環境や人に優しい自然な方法で、水質汚染や土壌汚染を解決し、個人や地域の環境保護に貢献しています。
また、バイオフューチャーの製剤は、メダカ飼育で使用する水槽のような小規模の水質改善だけでなく、湖沼や池などの大規模な水質浄化にも広く対応しています。実際に、全国の公共施設においても豊富な浄化実績があります。
メダカ飼育をはじめとしたアオコ問題でお困りでしたら、ぜひ下記のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。