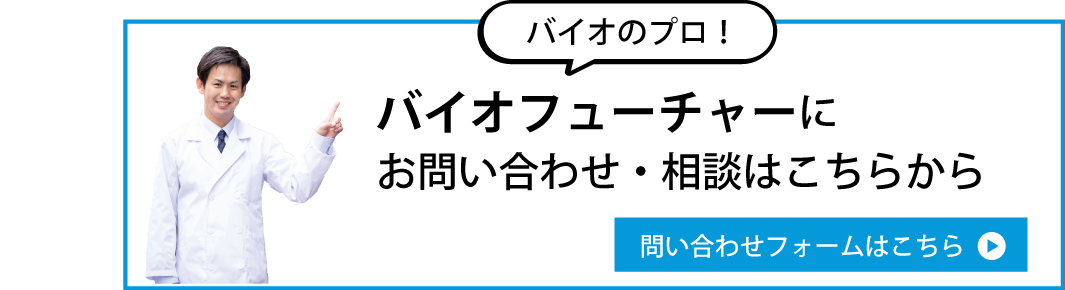水質汚濁や土壌汚染を防ぐためにできることを解説!どちらも浄化できるバイオ製剤の特徴もご紹介


水質汚濁と土壌汚染の原因と汚染を防ぐためにできることを解説します
近年、環境問題への意識が高まる中で、水質汚濁と土壌汚染は重要な課題となっています。これらは産業活動や農業、生活排水などによって引き起こされ、自然環境や人々の健康に深刻な影響を与えています。
水質汚濁は、有害物質が河川や湖沼に流れ込み、水生生物の生息環境を脅かします。また、土壌汚染は、有害物質が土壌や地下水に浸透することで、健康問題を引き起こす原因となります。
水質汚濁や土壌汚染の問題を解決するためには、環境保護への意識を高め、原因を正しく理解し、適切な対策を講じて防ぐことが重要です。
今回のコラムでは、水質汚濁と土壌汚染の原因とそれを防ぐための方法や対策、さらにバイオフューチャーによる浄化対策について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
土壌汚染の原因とそれを防ぐ理由
土壌汚染は、どのような原因で発生するのでしょうか。

土壌汚染とは、有害物質が土壌中に含有され、地下水を汚染する可能性があり、最終的には人々の健康に悪影響を及ぼす恐れがある状態を指します。日本では「土壌汚染対策法」に基づき、調査・対策が行われています。
土壌汚染が発生する主な原因は、事故や人的ミス、配管の経年劣化が挙げられます。特に工場などの施設から特定有害物質や油が流出することで、土壌汚染を引き起こします。土壌汚染が進行すると、人々の健康や環境に深刻な影響を与える可能性があります。
土壌汚染調査で汚染が確認されると、その土地は法律に基づき「要措置区域」として指定され、浄化や封じ込めといった対策が義務付けられます。これらの対策は土壌汚染を改善し、人々の健康や環境への影響を最小限に抑えるために非常に重要です。
浄化や封じ込めなどといった土壌汚染の除去方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
土壌汚染の除去方法を解説!環境や生物に優しいバイオによる浄化もご紹介!
水質汚濁の原因とそれを防ぐ理由
次に、水質汚濁が発生する原因についてご説明します。
水質汚濁とは、人々の健康や生活環境に悪影響を及ぼす可能性のある物質が、公共用水域や地下水に流入し、水質基準を超えてしまう状態を指します。「水質汚濁防止法」では、水質汚濁を防ぐことを目的として、公共用水域および地下水の水質保護を規定し、人々の健康や生活環境の保全を図ることが定められています。
水質汚濁の主な原因の一つは、工場排水や生活排水が適切に処理されずに河川に流れ込むことです。また、農薬や都市排水が雨水と一緒に流れ込むことも、水質汚濁の原因となります。
さらに、気候変動の影響も無視できません。温暖化により湖沼などの水温が上昇すると、アオコなどの植物プランクトンが異常発生し、生態系に深刻な影響を与えることがあります。
また、温暖化による酸性雨が河川や海に流れ込むことで、水質汚濁が進行し、生態系や環境全体へのリスクが高まります。

水質汚濁と土壌汚染は同時に防いだ方がいい?
水質汚濁と土壌汚染は、互いに密接に関係しています。
汚染された土壌には有害物質が含まれており、雨水などがその有害物質を地下水や河川に浸透させることで、水質汚濁を引き起こすことがあります。また、汚染された水が灌漑などに使用されると、その水が再び影響を与え、土壌汚染が進行することがあります。
このように、ひとつの汚染が別の汚染を引き起こすことがあるため、水質汚濁と土壌汚染の両者を同時に考慮し、対策を講じることが重要です。
水質汚濁と土壌汚染の関連性を理解し、それらを防ぐために総合的な対策を進めることが、環境保護において大切なポイントとなります。
水質汚濁と土壌汚染を防ぐ効果的な対策方法
水質汚濁と土壌汚染は、環境や生物に深刻な影響を与えるため、早期に防ぐためには効果的な対策が必要であることをご理解いただけたかと思います。 これらの問題を防ぐための対策として、大きく以下の3種類に分けられます。
- 1. 物質的処理
- 2. 化学的処理
- 3. 生物学的処理
それぞれの対策は、水質汚濁と土壌汚染それぞれの状態に応じて異なり、各々にメリットとデメリットがあります。 次に、水質汚濁と土壌汚染を防ぐためにできることや具体的な対策方法について、詳しくご説明しましょう。
水質汚濁を防ぐためにできることや具体策
まずは、水質汚濁を防ぐ方法と対策についてご説明します。
1. 物理的処理
吸着材やフィルター、沈殿などを利用し、有害物質を物理的に除去する方法です。
- ・メリット:即効性があり、短期間で処理できる。
- ・デメリット:すべての汚染物質を完全に除去するのは難しい。
2. 化学的処理
酸化剤や還元剤などの薬品を使用し、有害物質を無害化する方法です。
- ・メリット:効果が早く現れ、短期間での処理が可能。
- ・デメリット:薬品のコストが高く、使用する薬品の安全性に注意が必要。
3. 生物学的処理
微生物や植物を利用し、有害物質を分解する方法で、バイオレメディエーションが代表的です。
- ・メリット:環境に優しく、コストも比較的低く抑えられる。
- ・デメリット:微生物の力に頼るため、処理に時間がかかる。
土壌汚染を防ぐためにできることや具体策
続いて、土壌汚染を防ぐ方法と対策をご説明します。
1. 物理的処理
汚染された土壌をその場から取り除き、処理する方法です。代表的な方法は「掘削除去」で、取り除いた土壌は外部の処理施設に運搬・処分されます。
- ・メリット:短期間で確実に除去できる。
- ・デメリット:コストが高額になることが多く、環境への負荷が大きい。
2. 化学的処理
薬剤などを使用して有害物質を無害化する方法です。
- ・メリット:短期間での効果が得られ、物理的処理よりコストが抑えられることが多い。
- ・デメリット:薬品のコストが高く、処理後に残留物が残る場合がある。
3. 生物学的処理
微生物や植物を使って有害物質を分解する方法です。
- ・メリット:物理的処理や化学的処理と比べて低コストで、生物や環境への負荷も少ない。
- ・デメリット:浄化できる汚染物質の種類が限られており、処理には時間がかかる。
土壌汚染対策の種類や浄化工事の流れについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
土壌浄化工事はどんな工事?工事の種類や浄化事例をご紹介
バイオレメディエーションによる水質汚濁・土壌汚染浄化の特徴
水質汚濁と土壌汚染は、環境や生物に深刻な影響を与える問題であり、これを防ぐには適切な対策が必要です。
これらの汚染問題に対処するため、バイオフューチャーでは微生物(バイオ)の力を利用した「バイオレメディエーション」に特化し、水質汚濁や土壌汚染の浄化対策を行っています。

設立から29年という長年の豊富な知識と実績を持つバイオフューチャーは、お客様の状況に合わせて最適な浄化対策をご提案し、これまで多くのお客様にご満足いただいています。 ここからは、バイオフューチャーが行う水質汚濁・土壌汚染の浄化対策の特徴について、詳しくご説明します。
水質汚濁と土壌汚染両方の浄化に対応可能!しっかり防ぐことができる
土壌汚染が発生すると、地下水汚染も同時に進行することがあります。このような場合、バイオフューチャーのバイオ製剤と技術を活用した対策を行えば、土壌汚染と水質汚濁の両方を同時に浄化することが可能です。
バイオフューチャーが取り扱うバイオ製剤は、微生物を利用して土壌や水中の有害物質を分解します。そのため、環境への負荷が少なく、持続的な効果が期待できます。
水質汚濁や土壌汚染のいずれか一方のみの対策では防ぐことが難しく、汚染が拡大し、環境への影響が広がるリスクがあります。その点で、両方の浄化に対応できるバイオ製剤を用いた浄化方法は、近年注目される効果的な対策です。
安全なバイオで環境や生物に優しい対策方法
バイオフューチャーが取り扱うバイオ製剤は、安全性が非常に高く、環境への負荷が少ないため、土壌汚染や水質汚濁に対する優れた製品といえます。
バイオフューチャーのバイオ製剤は、微生物の力で有害物質を自然に分解します。これにより、化学薬品を使わず、環境や生物への影響を最小限に抑えることができます。さらに、バイオ製剤を使用することで、長期的な環境保護が可能になります。
一般的に、水質汚濁や土壌汚染を防ぐための対策としては、物理的処理や化学的処理という選択肢もありますが、これらは環境への負荷が大きいという懸念があります。
例えば、掘削除去は土壌を掘り起こすことで、環境破壊を引き起こす可能性があります。また、化学的処理で使用される薬品についても、安全性に対する慎重な配慮が必要であり、薬品が周囲の環境に悪影響を与えるリスクもあります。
これらの点を踏まえると、バイオ製剤を用いた対策方法は、環境や生物に優しい選択肢と言えるでしょう。
他の防ぐ方法と比べ安価に浄化可能
水質汚濁や土壌汚染の浄化には、物理的処理や化学的処理といった選択肢もありますが、これらの方法は高額なコストがかかることが多いです。
例えば、掘削除去では土壌を掘り起こすため、作業や廃棄にかかる費用が高くなります。また、化学的処理では薬品や処理にかかる費用が膨大になることもあります。
一方、バイオ製剤を使用した浄化方法は、比較的安価で、持続的な効果を得ることができるため、コスト面で非常に優れた対策です。
ただし、バイオ製剤を使用した水質汚濁や土壌汚染の浄化には、時間がかかるというデメリットもあります。微生物や植物の力を利用しているため、効果が現れるまでに時間を要します。しかし、環境への負荷が少なく、長期的には安価で持続可能な浄化が可能なため、総合的には有効な対策方法といえます。
バイオフューチャーの水質汚濁(地下水汚染)・土壌汚染浄化事例
バイオフューチャーが行った水質汚濁・土壌汚染の浄化事例をご紹介します。

【クリーニング工場跡地 – 宮城県】
汚染対象:土壌および地下水
汚染範囲:1,000 ㎥ 深度 GL 5.0m
作業期間:6カ月(浄化確認含め 約1年)
浄化方法:汲み上げバイオリアクター処理+バイオ注入方式
バイオ使用量:1,000L/月 × 6 か月 = 6 ,000L(1.0L/㎥)
- ・地下水の浄化結果
浄化前と各回の測定結果は以下の通りです。
(単位 : mg/L)
| 特定有害物質 | 浄化前 | 浄化後 |
| テトラクロロエチレン | 35 | 0.005 |
| トリクロロエチレン | 0.99 | 0.007 |
- ・土壌の浄化結果
浄化前と浄化後の土壌溶出量は以下の通りです。
| 特定有害物質 | 浄化前 | 浄化後 | ||
| 土壌 | 土壌 | |||
| 調査深度 | 土壌溶出量 | 調査深度 | 土壌溶出量 | |
| テトラクロロエチレン | GL – 0.5m | 0.038 mg/L |
GL – 0.05 ~10.0m |
< 0.001 mg/L |
| GL – 1.0m | 0.13 mg/L |
|||
| GL – 4.0m | 0.030 mg/L |
|||
| トリクロロエチレン | GL – 0.05 ~10.0m |
< 0.003 mg/L |
||
※基準値:
・テトラクロロエチレン:0.01mg/L以下
・トリクロロエチレン:0.03mg/L以下
水質汚濁と土壌汚染対策はバイオフューチャーにお任せください
水質汚濁と土壌汚染の対策は、バイオフューチャーにお任せください。

このコラムでは、水質汚濁と土壌汚染の原因やそれを防ぐ方法や対策、そしてバイオフューチャーが提供する効果的な浄化方法「バイオレメディエーション」についてご紹介しました。
水質汚濁や土壌汚染は、環境や人々の健康に深刻な影響を与えるため、その原因を理解し、効果的で環境に優しい対策を講じることが大切です。バイオレメディエーションは、自然な方法で有害物質を分解し、環境への負荷を最小限に抑える持続可能な対策方法です。
水質汚濁や土壌汚染の対策についてお考えの方は、ぜひバイオフューチャーにご相談ください。