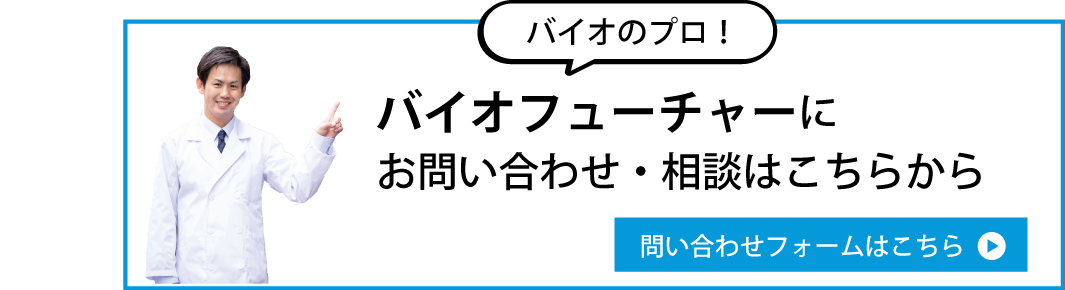池のヘドロ対策に!悪臭や水質トラブルをバイオの力で解決します


池にヘドロ・汚泥が溜まるのはなぜ?原因と水質への悪影響
池の水が濁ってきたり、底から悪臭が漂ってきたら、それはヘドロや汚泥の蓄積が原因かもしれません。
池はもともと水の流れが少なく、外部からの有機物が溜まりやすい環境になっています。そのため、適切なヘドロ対策を行わないと、徐々に水質が悪化し、景観や生態系にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。
池にヘドロや汚泥が発生するメカニズムを知ることは、根本的なヘドロ対策を進める第一歩です。
ここからは、池にヘドロや汚泥が発生する要因とその影響について、詳しく解説します。
池のヘドロ対策が必要となる原因
池にヘドロや汚泥が溜まる主な要因は、落ち葉や枯草、水生生物のフン、餌の食べ残しといった有機物が分解されずに、底に沈殿していくことです。
池の水は流れが少なく、酸素も不足しやすいため、こうした有機物が微生物によって十分に分解されず、汚泥として堆積してしまいます。また、池に流れ込む土砂や泥も、汚泥の量をさらに増やします。
定期的な清掃や水の循環が行われないと、このような汚泥の蓄積は加速し、水質悪化の原因となるのです。
そのため、ヘドロ対策としては、こうした有機物の管理と水の流れの改善が重要と言えるでしょう。

池のヘドロによる悪臭・景観悪化・生態系への悪影響
池にヘドロや汚泥が溜まり続けると、どのような影響があるのでしょうか。
まず気になるのが、悪臭です。特に、夏場など気温が高い時期には、腐敗した有機物から硫化水素などの臭気が発生し、周りに不快感を与えます。
加えて、池の水が黒ずんだり濁ったりして、景観も著しく悪化してしまいます。
さらに深刻なのは、生態系への影響です。酸素不足により水生生物が死んだり、藻類やアオコが異常繁殖することで、水中の生態バランスが崩れていきます。
このような悪循環を防ぐためには、早めにヘドロ対策を行うことが重要です。ヘドロ・汚泥を減らし、池の自然環境を守りましょう。
池のヘドロ対策にはどのような手法がある?
池に溜まったヘドロや汚泥を放置すると、水質悪化や悪臭、生態系への悪影響が深刻化します。このような問題に対処するためには、適切なヘドロ対策が必要です。

池のヘドロ対策には「物理的手法」「化学的手法」「生物学的手法」という3つの方法があります。それぞれ特徴や効果、費用、作業の手間などが異なりますので、池の規模や目的に応じて適切なヘドロ対策を選ぶことが大切です。
ここからは、各手法の具体的な方法やメリット・デメリットについて解説しますので、参考になさってください。
1. 池のヘドロ対策としての物理的手法
1つめの「物理的手法」とは、池の底に堆積したヘドロ・汚泥を直接取り除く方法です。例えば、吸引ポンプなどを用いて除去作業を行います。
物理的手法は即効性があり、池の見た目や悪臭が短期間で改善される点が大きなメリットです。ただし、大型の機械や人手が必要となり、施工規模が大きくなりがちです。また、作業中は池の生き物を一時的に避難させなければならないため、費用や手間もかかります。
短期的に池を改善したい場合に有効なヘドロ対策ですが、定期的な維持管理が必要である点を忘れないようにしましょう。
2. 池のヘドロ対策としての化学的手法
2つめの「化学的手法」は、特殊な薬剤を使用して池の汚泥やヘドロを分解する方法です。
酸化剤などの薬剤を投入することで、比較的短期間で水質を改善し、ヘドロ対策として一定の効果が得られます。
しかし、薬剤の使用には注意が必要です。水中生物に悪影響を与えるリスクや、投入量の管理ミスによって二次被害になる恐れもあります。また、継続的な効果が薄く、一時的な対処に留まることが多いです。
水生生物や環境に配慮するためには、他のヘドロ対策と組み合わせて使用するのがおすすめです。
3. 池のヘドロ対策としての生物学的手法
3つめの「生物学的手法」は、微生物やバクテリアといった自然の力を利用して、池に溜まったヘドロや汚泥を分解する、環境に優しいヘドロ対策です。
バイオ製剤を定期的に池に投入することで、落ち葉や水生生物のフンなどの有機物が分解され、池の水質が少しずつ改善していきます。即効性は高くありませんが、継続することで安定した効果が期待でき、自然の生態系を損なわずにヘドロ対策を行うことができます。
また、大がかりな装置や作業が不要で、ご家庭の池にも手軽に導入できる点も魅力です。
バイオ製剤を定期的に投入し、池の状態を見ながら継続することで、負担をかけずにしっかりヘドロや汚泥を減らせる、実用的な方法と言えるでしょう。

ヘドロが溜まる原因と予防のポイント
水の流れが少ないことが、池にヘドロが堆積する主な原因のひとつであることは、前述のとおりです。
池は閉鎖性水域であるため酸素が不足しやすく、微生物による有機物の分解が進みにくくなります。その結果、落ち葉や水生生物のフンなどが分解されずに溜まり、ヘドロとなって水質が悪化してしまうのです。
このような原因に対しては、エアレーションなどで水中に酸素を供給すること(曝気)が効果的です。酸素を取り込むことで、微生物の分解活動が活発になり、水質改善につながります。
特に、微生物を活用する「生物学的手法」と組み合わせることで、相乗効果が期待できます。
さらに汚泥の蓄積を防ぐには、酸素の供給だけでなく、定期的な落ち葉やゴミの除去、流入口にフィルターを設置して土砂流入を防ぐなど、日常的な管理も欠かせません。
こうした予防的な対策を取り入れることで、ヘドロ対策の効果を高め、池の水質をより安定させることができます。
池のヘドロを分解!バイオフューチャーのバイオを活用するメリットとは
バイオフューチャーのバイオ対策について、具体的にご説明します。
バイオフューチャーは、設立から30年の実績を誇るバイオ専門会社で、微生物を活用した「バイオレメディエーション」技術に特化しています。自然環境に優しく、持続可能な方法で、池の汚泥やヘドロの分解をサポートします。
庭池のような小規模な池から、公園や施設にある大規模な池まで幅広く対応可能です。バイオ製剤の使用方法もシンプルで、初めての方でも安心してご使用いただけます。
ここからは、バイオフューチャーが提供するバイオ製剤の特徴や使用方法について、具体的にご紹介しましょう。
安全性が高く環境に優しい液体バイオ製剤で池の水質を改善
バイオフューチャーが提供する液体バイオ製剤は、化学薬品を使わず、微生物の働きによってヘドロや汚泥を自然に分解するため、生態系への負担が非常に少ないのが大きなメリットです。
また、バイオフューチャーのバイオ製剤は、短期間で効果を出すよりも、原因を根本から解決し、長期的に池の水質を安定させることを目的としています。そのため、バイオ製剤を繰り返し使用することで、池に優しく、持続可能なヘドロ対策が可能になります。
環境への影響を重視したい方にとって、バイオ製剤によるヘドロ対策は非常におすすめの選択肢と言えるでしょう。

小規模な池から公共池まで幅広く対応
バイオフューチャーのバイオ製剤は、家庭の小さな池から公園や自治体が管理する大規模な池まで、さまざまな規模に対応できる柔軟性を備えています。
池の状態や使用目的に応じたヘドロ対策をご提供できますので、個人の利用者はもちろん、環境整備に取り組む行政や企業にも活用されています。
バイオフューチャーのバイオ製剤はどのような池でも導入でき、場所を選ばず効果的なヘドロ対策が実現できますので、どうぞお気軽にご相談ください。
初心者でも扱いやすいバイオ製剤
バイオフューチャーのバイオ製剤は、簡単に取り扱える点が魅力です。そのまま池に投入するだけで、ヘドロや汚泥を徐々に分解していくため、複雑な工程や大がかりな設備は必要ありません。
「ヘドロ対策を行いたいけれど、方法がわからない」という初心者の方に安心して使える仕様になっています。
また、バイオフューチャーが取り扱うバイオ製剤の微生物は、納豆菌と同レベルの安全性ですので、決められた使用量をきちんと守れば、水生生物だけでなく人への影響も最小限に抑えられます。
手軽で効果的な池のヘドロ対策として、バイオフューチャーのバイオ製剤は多くの現場で活用されています。

バイオフューチャーの液体バイオ製剤をご紹介!ヘドロ対策の効果と特徴
バイオフューチャーでは、ヘドロ対策に活用できる4種類の液体バイオ製剤を取り揃えています。
- 1. 液体バイオ製剤FM
- 2. 液体バイオ製剤ST
- 3. 液体バイオ製剤マイクロブリフト
- 4. 観賞池向けバイオ製剤
いずれのバイオ製剤も、自然由来の微生物パワーでヘドロ対策ができます。
小さな庭池から公共の大規模池まで対応でき、初心者でも扱いしやすい製剤です。化学薬品に頼らず池の有機物を分解し、長期的に水質を改善することができます。
次に、各バイオ製剤の特徴を詳しくご紹介します。
1. 液体バイオ製剤FM
「液体バイオ製剤FM」は、好気性の微生物を主成分とした液体タイプの製剤で、池のヘドロ対策に効果的です。
リンや窒素を分解する働きがあり、水質改善に役立ちます。特に、池の底に堆積した汚泥の分解に優れています。
また、COD(化学的酸素要求量)やBOD(生物学的酸素要求量)、SS(浮遊物質)の数値を改善し、池の水環境全体を健全に保つ効果が期待できます。
さらに、悪臭の低減といった副次的効果もあるため、ヘドロ対策と同時に快適な池環境を維持したい方に最適です。
後述する「液体バイオ製剤ST」や「液体バイオ製剤マイクロブリフト」と併用することで、より高い相乗効果が得られます。
2. 液体バイオ製剤ST
こちらの「液体バイオ製剤ST」も、「液体バイオ製剤FM」と同じく好気性の微生物を使用した液体タイプの製剤で、ヘドロ対策としておすすめです。
植物や落ち葉などに含まれる有機物(セルロース)の分解に優れた微生物を含んでおり、池の底に溜まった汚泥や有機物を効率良く分解します。これにより、悪臭の抑制や水の透明度向上といった効果が期待できます。
さらに、「液体バイオ製剤FM」や「液体バイオ製剤マイクロブリフト」と併用すれば、それぞれの特性を活かしながら相乗的な効果が見込めますので、ヘドロ対策にぜひご使用ください。
3. 液体バイオ製剤マイクロブリフト
「液体バイオ製剤マイクロブリフト」は、好気性菌と嫌気性菌を12種類配合した高機能バイオ製剤で、池のヘドロ対策に優れた効果を発揮します。
酸素が届きにくい池の底でも活性を維持し、汚泥や有機物をしっかり分解します。また、汚泥を除去することで、水質改善や悪臭・BOD・SSの低減にも役立ちます。
環境の酸性・アルカリ性を問わず、幅広い池の環境に対応できるという利点もあります。
「液体バイオ製剤FM」や「液体バイオ製剤ST」と併用することで、相乗効果が生まれ、池のヘドロ対策をさらに強化できます。
4. 観賞池向けバイオ製剤
「観賞池向けバイオ製剤」は、「液体バイオ製剤ST」「液体バイオ製剤FM」「液体バイオ製剤マイクロブリフト」の3製品を配合し、個人宅の池やビオトープ、小規模な景観池に特化したヘドロ対策用のバイオ製剤です。 
光合成細菌を含む複数のバクテリアが、池の底に溜まったヘドロ・汚泥や有機物を分解します。また、水の透明度を高め、悪臭を抑えるなど、水質改善に優れた効果を発揮します。
鯉や金魚などの観賞魚、水草にも無害な成分で構成されており、安全に使えるのも魅力です。簡単に使用できるため、手間をかけずに池の景観と生態バランスを保ちながらヘドロ対策をしたい方に最適なバイオ製剤です。
バイオフューチャーによる池の浄化対策事例
バイオフューチャーのバイオ製剤が、実際にどの程度の効果を発揮するのか気になる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、過去にバイオフューチャーが実施した池の浄化対策事例をご紹介します。
| 場所 | 北海道 修景池 |
| 要因 | 汚泥の堆積 |
| 処理方法 | 液体バイオ製剤ST、FM、マイクロブリフトの投入 |
| 浄化期間 | 5週間 |
| バイオ使用量 (総量) |
液体バイオ製剤ST 15L 液体バイオ製剤FM 15L マイクロブリフト 6本 |

【調査結果】
- ・バイオ製剤投入前:緑色の堆積汚泥 深さ約15㎝

- ・バイオ製剤投入後(5週間後):緑色の堆積汚泥 深さ約3㎝

昨今では、池の景観回復だけでなく、生態系にも優しい方法として、導入をご検討される管理者やご家庭からのご相談が増えています。「見た目も水質も改善したい」「持続可能なヘドロ対策を探している」という方は、お気軽にお問い合わせください。最適なバイオ製剤の組み合わせや使用方法をご提案いたします。
池の汚泥・ヘドロ対策でお悩みの方はバイオフューチャーへご相談を!
池に溜まった汚泥やヘドロの対策でお困りの方は、バイオフューチャーにお任せください。

このコラムでは、池のヘドロが発生する原因や悪影響、そしてバイオフューチャーのバイオ製剤による効果的な改善方法について、詳しく解説しました。
池のヘドロ対策では、一時的な除去ではなく、根本から解決する持続的な方法を選ぶことが大切です。バイオフューチャーのバイオ製剤なら、初心者でも簡単に扱うことができ、使用量をきちんと守れば池のヘドロの分解や水質改善を効率良く行えます。
環境や生態系への影響が少ない安全なバイオ製剤を使って、手軽に池の水質改善を行いませんか。ご質問やご相談は、どうぞお気軽にバイオフューチャーまでお問い合わせください。